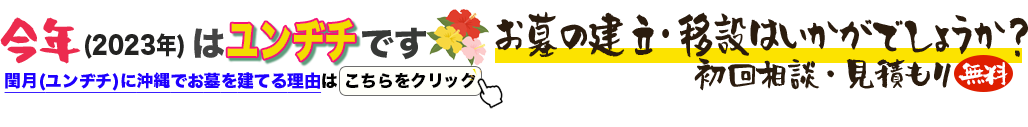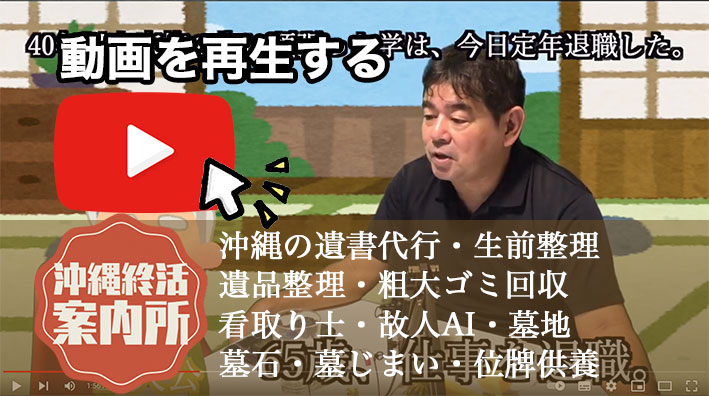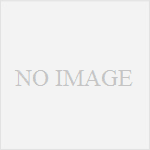目次
犬や猫などのペットは相続の対象となる? 遺産相続はできるのか
犬や猫などのペットは、法律的解釈では「動産」になりますので、相続財産として扱われます。そのため、遺産相続の対象になります。
皆さんもご存じ通り、相続財産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」があり、その「プラスの財産」と「マイナスの財産」を合算して、全体の相続財産を評価するのですが、一般的にペットを評価する際は「評価ゼロ」として扱われます。
ここで問題になるのが、ペットをスムーズに遺産分割できるのか? という事です。被相続人と相続人が同居していた場合は比較的スムーズに進むと思いますが、そうでない場合はどうでしょうか? 飼育環境の問題、住宅環境の問題、動物アレルギーの問題、そして飼育費の問題。様々な問題が噴出してきます。
さらに、平成25年に施行された「改正動物愛護管理法」において、ペット飼養者に対して「終生飼養」を義務化する文言が追加されました。これは、犬や猫などのペットを一旦迎え入れた場合、その個体の面倒を生涯に渡り、見届けなくてはならないというものです。
「終生飼養」という文言が追加された背景としては、一時的な感情により、安易にペット達を迎え入れてしまい、ペット達と生活していく中でその感情が冷めてしまい、飼主の一方的な都合により保健所へ持ち込まれた結果、犬猫の殺処分が年々増えていたという社会背景があります。
犬や猫などのペット達は、法律的には「動産(物)」として扱われますが、「終生飼養」を義務化した事により、飼主の「命」に対する責任を明確にしたのではないかと思います。
認知症の進行プロセス(各種資料を基にBeyond Health作成)
今後のヘルスケアの課題は、できるだけ早期にMCI者を発見し、その段階から適切な対策をすることで認知機能の低下を遅らせることだ。
国立長寿医療研究センター病院の近藤和泉院長は「これまで、認知機能の低下を遅らせる取り組みとしては運動指導、認知トレーニングなどが行われてきました。
いずれも単独では有効性が実証されていないものの、いくつかを組み合わせれば効果が得られるという研究報告があります」と解説する。
国立長寿医療研究センター病院の近藤和泉院長(写真提供:国立長寿医療研究センター)
指の運動を解析しMCIを早期発見
こうしたMCI進行抑制に関する研究が進むなか、その成果を最大に生かすためにもMCIの早期発見技術の開発が欠かせない。
特に認知症の中でも最も多いアルツハイマー型認知症は、発症の20年ほど前から主な原因物質であるアミロイドβが脳内に蓄積し認知機能の低下をもたらす。
これまで発売されてきたアルツハイマー病の治療薬は症状を抑えるものだったが、いま開発されているのは、アミロイドβに直接作用して進行を抑える薬剤だ。
現在、エーザイが開発しているレカネマブ(一般名)は、開発の最終段階である臨床第3相試験の結果がまとまり、近い将来、治療薬として使われる可能性がある。
近藤院長は「こうした今後開発される治療薬の有用性を最大にするためにもMCI早期発見が重要です」と話す。
現在、MCIのスクリーニングとしては、血液検査でアミロイドβの蓄積に関連するバイオマーカーを調べたり、脳MRI、脳FDG-PETなどの画像診断があるが、いずれも採血や費用など患者の負担が大きいのに検査精度は期待通りではないという。
世界中の研究者が新たな診断方法の開発に取り組むなかで、近藤院長が注目したのは指の運動機能だ。
「指の運動には脳の広い領域が関与しており、アミロイドβの蓄積による神経機能の異常を早期に捉えられる可能性があります」と近藤院長は解説する。いわば指の動きで「脳をみる」技術だ。
5分ほどで早期診断につながる指タッピング運動を解析
近藤院長の研究は、2010年、指運動機能を短期間かつ簡便な方法で解析するデバイスが登場したことで動き始めた。
それは日立製作所が開発した「磁気センサー型指タッピング装置」だ。タッピング(tapping)とは、何かを素早く軽く叩くときの動作を表す英語だ。
日立製作所の装置は、非常に薄い磁気センサーを人差し指と親指の先につけることで、指の動きを精密に捉えるもの。具体的には人差し指の先端と親指の先端を繰り返し叩く運動(タッピング)から得られた運動波形を解析することで、指の運動機能にかかわる脳の状態を評価する。
当初、日立製作所の研究開発グループは、脳の疾患のなかでも進行すると手の震えや歩行困難など運動障害を示すパーキンソン病の早期診断に役立てることを考えていたが、認知症でも脳内の電気活動の遅れを反映した指タッピング動作の異常を発見し、相談にのった近藤院長は一目見て「これは認知症の診断に使える」と感じ、共同研究がスタートしたという。
指タッピングの運動波形でMCIの兆候を検出
研究に用いた「磁気センサー型指タッピング装置」は非常に精度の高いもので、「タッピングの速さとその変化」「ふるえ」「両手で行ったときの同調」など23種類の指の運動パターン(特徴量)を、運動波形として解析できる。
近藤院長と国立長寿医療研究センターの研究グループは、まず少人数の試験で認知障害のある場合と健常な場合で、異なる運動波形になるものがあることを確かめた。
そして、2019年から本格的な臨床研究をスタートさせた。
ちょうどその頃、「磁気センサー型指タッピング装置」の事業が日立製作所からマクセルに委譲され、マクセルが「磁気センサー型指タッピング装置UB-2」を研究用機器として製品化したこともあり、大規模な研究が実現することになった。検出できる運動パターンの違い(特徴量)も44種類に拡張された。
マクセルが製品化している「磁気センサー型指タッピング装置UB-2」(写真提供:マクセル)
臨床研究は、軽度認知障害グループと対照グループ(健常高齢者)それぞれ173名で行われた。
被験者が行ったのは、「左右片方の手でタッピング運動を行う」「両手同時に行う」「左右交互に行う」の3つの運動だ。
近藤院長は「軽度認知障害グループと対照グループでは、複数の特徴量に違いが見られたが、なかでも4つの運動量には明確な差があり、その変化に注目すればMCIの早期診断が可能になると考えられました」と解説する。
タッピング回数や運動のばらつきにMCIの特徴が見られた
研究成果は2022年8月、Hong Kong Journal of Occupation Therapy に掲載された。
掲載データによると、軽度認知障害グループと対照グループでは、「一定時間でのタッピング回数」「タッピング間隔」「タッピング間隔のばらつき(標準偏差)」「すくみ回数」に特に大きな有意差(統計学的に見ても明らかな差)が見られた(下グラフ)。
「すくみ」というのは指をくっつけたときに、なかなか離せなくなる現象だ。
例えば、MCI群で全体のタッピング回数が減ったり、連続したタッピング動作の間隔が広がったりしているのは、脳の神経細胞の一部の機能が低下していることを意味していると考えられる。
機能低下しているだけで、機能を失っているのではないのでタッピング自体は可能だが、シナプスの伝達効率などが、微妙に低下して、影響していると考えられる。
タップ運動自体はフィードフォワード制御で、予め決められた運動プログラムを行っているだけなので、微妙な調整を脳が行っているわけではない。
このためどのパラメータの異常で、どのパラメータが正常に近い値を出しているかは、あまり意味がない。むしろ早期に異常が出やすいパラメータを予め特定しておき、異常値が出た時に火災報知器的な役割を果たしてくれることが期待される。
近藤和泉院長らが行った「磁気センサー型指タッピング装置UB-2」を使った解析結果。解析した44の特徴量のなかで、グラフに示した4項目でMIC者と健常高齢者の差が顕著に見られた
簡便な軽度認知症のスクリーニング技術で職場健診も実現
今回の論文では、指の運動を測定するという患者に負担の小さな方法で脳の認知機能の低下を評価できる可能性を示した。
この研究成果について近藤院長は、「UB-2はコンパクトで、専門家でなくても使いこなせる装置であることがポイントです。将来は、職場健診などに応用できると考えています。ただし、その実現のためには課題もあります」と話す。
1つは、人々の中には一定の割合で生まれつき指を使った細かい作業が苦手な「発達性協調運動障害」の人がいるということだ。
例えば小学校では音楽の授業に「縦笛」を使うが、うまく指を動かせない子供がいたりする。
近藤院長は「今後は、UB-2 で測定できる運動パターンをより精査し、発達性協調障害と軽度認知障害を区別できるようにしたい」と考えている。
近藤院長が考える「軽度認知障害の早期発見のための検診・健診プラン」とはどのようなものなのだろう。
40歳で始まる軽度認知症検診
まず、簡便な指タッピング運動による検査を職場健診などで行う。
そして、リスクがあると考えられた人に精密検査を促すというものだ。ただ、指タッピング運動による検査はMCIの大規模なスクリーニングに適しているが、かなり早期の脳機能の低下もキャッチするため、精密検査が必要になる。
近藤院長は「ノーベル賞を受賞した田中耕一氏が開発した技術を用いて、わずかな血液から感度のいいバイオマーカーを見つける検査が登場しており、指タッピング運動の検査との組み合わせに期待したい」という。
これは島津製作所が「血中アミロイドペプチド測定システム Amyloid MS CL」として提供している検査だ。現時点では検査費用が高いため集団健診には向かないが、指タッピング運動を用いた検査システムの改善とバイオマーカー検査の低コスト化の両方が実現すれば認知症の診断と治療は大きく変わる可能性がある。
では、近藤院長の目指す認知症検診が実現したとき、何歳ぐらいで受けたらいいのだろう。
近藤院長は「ずばり40歳です」という。アルツハイマー型認知症は、脳内のアミロイドβが20年以上蓄積して発症することが明らかになっている。
将来アルツハイマー型認知症を発症する人では、40歳ぐらいから自分でも家族でも気づかない程度の脳機能の低下が始まっている。
軽度認知障害が早期に発見できれば、予防のためのヘルスケアの重要性も増してくる。
認知症を進めないコツは「ストレス回避」
こうした研究によって、近い将来、より科学的エビデンスに基づく認知機能低下の進行予防が実現するだろう。
しかし一方、近藤院長は、「こうした将来の話に注目するだけではなく、今分かっている認知障害についての正しい知識を啓蒙・実践することも大切です」と話す。
その1つが「根拠のない間違ったケアをしないこと」だ。難しいことではない「認知症者に余計なストレスを与えない」ためである。
近藤院長は「患者さんには、できるだけ従来通りのやり方で生活を送ってもらうことが大切です。
私の外来でも、それで徘徊や妄想を起こさず平穏な暮らしを続けている方が沢山おられます」とアドバイスする。
「脳をみる」新たなアプローチより引用しました。 荒川 直樹=科学ライター 2023.1.18