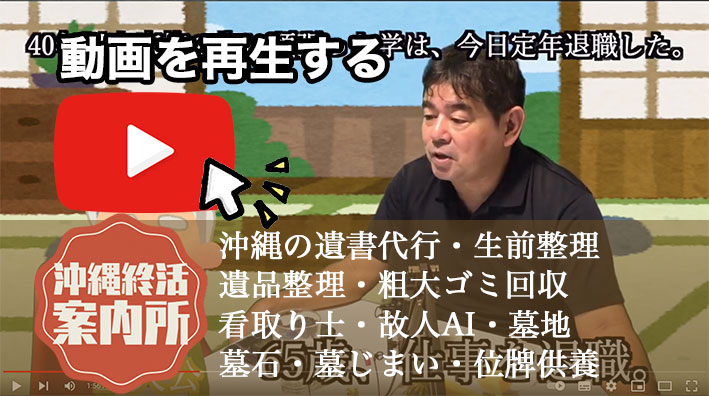前回の記事で、お墓の歴史を振り返ってみました。一方、高齢化や人口の都市集中、さらにコロナ禍によってお墓参りがしづらい時代になっており、お墓参り代行サービスも出現しています。
今後、お墓参りはどのようにしたらいいのか。それを考える前に原点に立ち返り、お墓参りはどのように始まり、どんな経過をたどって現在のような習慣になったのかについて知ることは大切です。
そこで今回は、前回のお墓の歴史を検証した話とセットで、お参りの歴史についても振り返ってみましょう。
お墓がなければお参りはできない・・・
お墓参りは、故人をしのんで感謝の念を捧げ、同時に家族の近況を報告する行為といえます。精神的な要素が非常に強いですね。
しかし、あえて即物的に表現すると、遺骨の入った骨壺を収めた石の建物に手を合わせること、といういい方もできます。
つまり、お墓という、目に見える「物」があってこそ、お参りという行為が可能なのであり、その意味ではお墓とお参りはセットなのです。当たり前ですが。
したがって、お参りの歴史を考えるとき、お墓の歴史も密接に関わってきます。そのあたりは頭に入れておきたいと思います。
キリスト教禁教にお寺が利用される

仏教が日本に入ってきたのは6世紀の中ごろ。まだ飛鳥時代のころでした。一方、キリスト教が伝来したのは16世紀の中ごろで、仏教に遅れること1000年、戦国時代でした。
フランシスコ・ザビエルらの宣教師は日本でのキリスト教布教を開始し、それを織田信長といった大名が庇護したこともあって、順調に信者を増やしていきました。
しかし、ご承知のように、江戸幕府はキリスト教を禁止し、それによって次第に寺請・檀家制度が整えられていきます。
この制度は、自分がキリシタンではなく仏教徒であることをお寺に証明してもらうものです。お寺からは寺請証文というものを発行してもらいましたが、それがないとキリスト教徒と見なされ、下手をすれば処刑されかねません。命に関わる証文でした。
そのため、住民は指定のお寺に所属、つまり檀家にならざるを得ませんでした。権力側はこのようにお寺をキリシタン監視機関および戸籍担当のように利用し、行政の末端機関の役割を押しつけたのです。
その代わりとしてお寺は檀家のお葬式や法要などの仏事を独占的に行う権利を得たのでした。これが現在も残る檀家制度の元になっているわけです。
ニセ文書が出て檀家制度が確立

さらに、宗門檀那請合之掟(しゅうもんだんなうけあいのおきて)という文書が発布されます。その主な内容は「葬儀や法要は必ず檀那寺で行うこと」「寺院の建物の建立や修理にお金を出すこと」「お布施を払うこと」「戒名を付けること」「檀那寺を変えないこと」などというものでした。
この文書は徳川家康が出したものとされましたが、実はニセ文書であったというのが現代の通説です。だれが、どんな目的でニセ文書を配布したのかは定かではありませんが、お寺にとってきわめてメリットのある内容であることは確かです。
実際、この文書が出たことでお寺の経営は安定しました。このあたりがいわゆる葬式仏教の始まりになります。お寺にお葬式や法要をお願いし、戒名をつけてもらって、おうちで位牌を拝むという現在の風習は、このように江戸時代に出たニセ文書によって確立されたといってもいいわけです。
禁止されていた庶民のお墓建立
さて、お墓ですが、前回の記事でも書いたように、江戸時代に入っても一般庶民はお墓を造りませんでした。決められた場所に穴を掘り、お棺に入れた遺体を埋め、その上に土饅頭を置くというスタイルが一般的でした。
遺体が腐敗し、お棺も腐ると土饅頭ごと土が陥没して平坦な地に戻ります。そうなると目印がないので、お骨がどこに埋まっているかわからなくなり、お参りのしようがなくなります。
実は、庶民がお墓を建てられないのは、法的に禁止されていたからです。ただし、上流階級では、遺体を葬ったのとは別の場所に石塔を建て、これをお参りしたりしていました。
江戸時代後期にやっとお墓が解禁

一方、1831年になると「墓石制限令」というものが出ます。庶民がお墓を建てる時の高さなどを定めたもので、逆にいえば、定められた条件を満たせば庶民でもお墓を建てていいという、実質的な許可令でした。
したがって、一般庶民がお墓を建てられるようになったのは、江戸時代も後期になってからということになります。今から170年ほど前のことですね。なので、今のお墓にまつわる風習は、お参りも含めて、このころから始まったと考えられます。
まとめ
このように、お墓参りの習慣ができてからまだ200年も経っていません。古くからの慣習というわけではないのです。
時の権力者のおもわくや、誰が出したかもわからないニセ文書など、さまざまな事情で葬式仏教ができあがり、それが結果的にお墓を巡るあれこれに影響を与えているようです。
したがって、現在のお墓参りのスタイルは未来永劫に守られるべき、というわけでもなさそうです。時代の要請に応じて、変化していくのもありなのではないでしょうか。