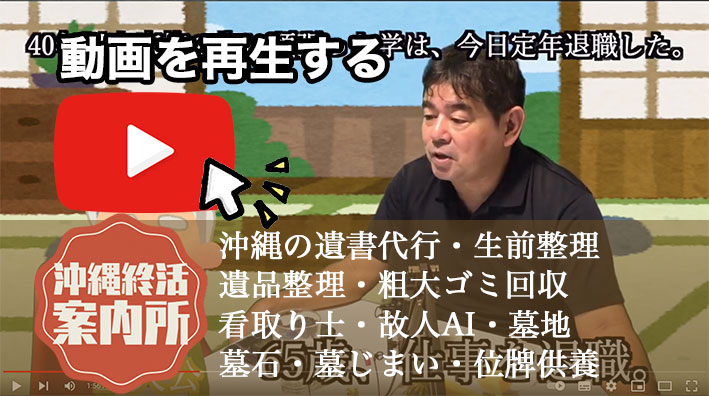以前のこのコラムで、葬送法の変化について書きました。日本でも昔は土葬で、現在は99%が火葬になっているというお話です。
この変化はお墓の形式にも影響を与えました。土葬と火葬ではお墓のスタイルが違うのは当然ともいえます。
今回は、日本における葬送法の移り変わりと、それによるお墓の変化について見ていきます。
政府が火葬禁止令を出した?

火葬は仏教とともに日本に入ってきたといわれます。ただし、仏教の普及とともに火葬も一般的になったわけではありません。一般庶民の間では、第二次世界大戦まで大部分は土葬でした。
また、明治政府は天皇による国家統治を強力に推し進めるため、その根拠として神道を国教化する方針を固めました。これに沿って仏教を否定する路線を打ち出したため、その流れで火葬禁止令が一時出されるほどでした。これは、神道が火葬を残酷な葬送法ととらえていたことによるものです。
こうした流れもあってか、明治の半ばごろまで日本の火葬率は全体の1割程度にすぎませんでした。
土葬墓の石が墓標や墓石に発展

土葬では、遺体を棺に納めて土の中に埋めます。土葬用の棺には2種類ありました。寝棺と座棺です。寝棺は現在の棺とほぼ同様のタイプ。座棺は遺体を座った姿勢で入れるタイプです。
いずれにも、三途の川の渡し賃としてお金を入れることがありました。三途の川が仏教の概念だとすると、仏教の考え方と土葬という土着の習慣が入り混じっていたとも思われます。
また、土中の棺はいずれ腐り、ふたが落ちるので、地表に穴が開きます。それを想定して埋めたあとに大きな石を置くことがありました。これが墓標や墓石に発展していったといわれています。
火葬は残酷だという発想が日本人にはない

第二次大戦後、火葬への転換の流れが急加速します。その要因として急速な都市化や火葬技術の向上があげられますが、日本人の遺体に執着しない精神性も大きなバックグラウンドになっていると思われます。
キリスト教徒やイスラム教徒などは、死者はいずれ復活するので肉体を残しておこうと考えますが、無宗教者の多い日本人にはそんな発想がありません。
仏教も遺体の扱いには比較的無頓着な面があります。死後硬直した遺体の手足をバキバキ折り曲げて座棺に納めても平気、という態度が遺体に対する日本人の姿勢を象徴しているように思えます。
宗教的な縛りが少なく、葬送法にそれほどこだわらない日本人にとっては、火葬は合理的で近代的なおくりかたともいえます。
個人墓から家墓への転換

一方、土葬から火葬への転換は、当然のようにお墓のスタイルも変えました。現在でも多く見られる家墓が現れるのは江戸時代も末期のことです。さら、それが一般にも普及するようになったのは明治の末ごろです。
常識的に考えて、一体一体土葬にしていた昔は個人墓が基本で、現在のような家単位の墓は少なかったのではないでしょうか。火葬するようになったからこそ、代々の人がひとつのお墓に入れるようになったと考えられます。
芸術の域に達した火葬技術

ところで、語弊があるかもしれませんが、現在の火葬技術は芸術の域に達しているともいえます。
戦前は座棺が多かったのですが、戦後になって寝棺の割合が急ピッチで増えます。座棺では、焼き上がった骨はひとかたまりになるので、それを骨壺に移せばよかったのですが、寝棺になったことで少し様子が変わってきました。
寝棺に入った遺体を台車式の火葬炉で焼くようになったため、骨格が原型通り焼き上がるようになりました。係員の技術も進歩して、焼き方もうまくなりました。焼き足りないのはまずいし、焼きすぎてもいけません。その微妙なさじ加減が火葬技術を芸術の域にまで押し上げたといわれます。
そのおかげで、骨揚げも様式化しました。遺族は台車をはさんで向かい合い、2人1組になって竹、木、または金属の箸でお骨を拾いあげて骨壺に入れていき、交代しながらこれをくり返します。拾う順番も、足、腕、腰、背骨、ろっ骨、頭蓋骨という具合に決まってきました。
そして、地域によっては喪主がのど仏を拾って骨壺の一番上に納めます。のど仏は、仏さまが座禅を組んでいるように見えるところから特別扱いされるようになったといわれています。
まとめ

骨格を原型通りに残したり、それを決まった順番に骨揚げするのは日本独自の葬送習慣です。それがあるので、とにかく焼けばいいというわけにはいきません。
そのため火葬炉に工夫を凝らし、徹底的に技術を磨いたのです。日本の火葬は単なる遺体処理の一手段ではなく、まちがいなく文化といえるものでしょう。
その発達にともなって進化してきたお墓も、また文化と呼べるものなのです。