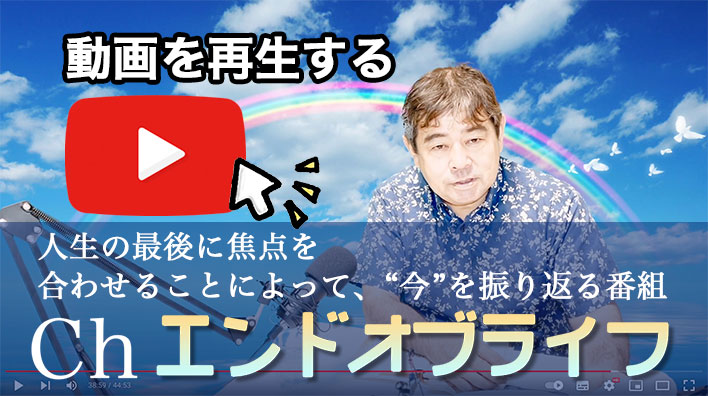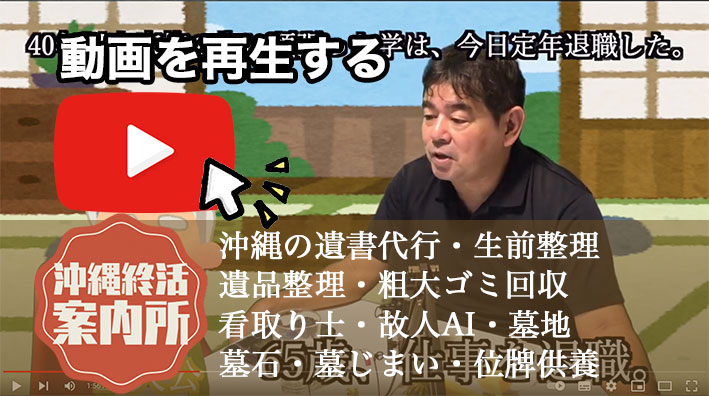沖縄には大きなお墓がたくさんあります。大きくて見事な亀甲墓などはほとんど文化財クラスで、観光客の方が来るようなところもあります。王様や超有名人のお墓ならともかく、一般人の個人墓が観光資源になるという話は、県外ではあまり聞いたことがありません。
県外から来た人といっしょに、そうした大きなお墓を見ているとき「沖縄のお墓って、なぜこんなに大きいの?」と聞かれたことがあります。そのときはとっさに「門中(むんちゅう)墓だから」と答えました。
すると「門中墓ってなに?」と重ねて聞かれました。「門中のみんなが入るお墓」と答えましたが、相手はまだ納得していない顔をしていました。それもそのはずです。答えた自分だってよくわかっていないのですから。
そこで、知っているつもりでも実はよく知らないかもしれない「沖縄の墓はなぜ巨大なのか」について整理してみます。
先祖崇拝を背景とする門中制度

ウチナーンチュの日常生活において、先祖崇拝の意識が強いことはよく知られています。沖縄の先祖崇拝は個人の暮らしはもちろん、社会の基盤となっているといってもいいでしょう。したがって、同じ先祖を持つ家族や親族間の結びつきも大変強いものがあります。
この、親族間の強い結びつきが発展したのが門中です。したがって、門中とは血族集団ともいえるのですが、もうひとつの特徴は父系だということです。つまり、父方の血筋に属している親族の集まりが門中だと定義できます。
たくさんの家族で所有する門中墓

沖縄では、この門中という集団でひとつのお墓を所有するケースが多く見られます。それを門中墓というわけです。
似たようなお墓に家族墓があります。しかし、家族墓が、ひとつの家族でひとつのお墓を持つのに対し、門中墓はたくさんの家族でひとつのお墓を所有するケースが多いのです。大規模なものになると、数百もの家族でお墓はひとつという場合もあります。
そうなると、当然人数は多くなります。場合によっては数千もの人でお墓を共有することもあり、実際に沖縄には5000人くらいのお骨が納まっているお墓も存在します。お墓が大きくなるのは当然ともいえます。
したがって、個人墓<家族墓<門中墓という感じで大きくなっていくわけですね。
合理的で道徳面でも役立つ門中墓
ところで、俗な発想ですが、門中墓は大きいけれどもコスパはいいということもいえます。つまり管理や行事にかかる費用は門中に属する家族で分担すればいいわけです。一家族で年間数千円程度を負担すれば、お墓の掃除やメンテナンス、シーミーなどの行事の際の費用をまかなうことができるので、効率はいいのですね。
また、門中に属する子どもたちや若者に対して「悪いことしたら、死んだ後お墓の中でご先祖様に怒られるぞ」といえば、かなりの効果が期待できます。道徳的な面からも門中墓は役立つといえます。
巨大な理由のもうひとつは風葬習慣
ところで、お墓が巨大な理由はもうひとつあります。それはかつての沖縄では風葬が一般的だったことです。風葬についてはこのコーナーで粟国島における洗骨とセットで紹介したこともありましたが、つまり、遺体を火葬したり埋葬したりせず外気にさらして風化させることです。
時代や地域によって違いもありますが、棺に入れた遺体を洞窟や岩陰に置いたり、お墓の中に入れておいて、何年か経ってから遺骨を洗い、骨壺などに納めたりします。
風葬を前提としたお墓の場合、内部は遺体を安置する部屋と、洗骨後のお骨を安置する部分のふたつに分かれているのが一般的です。
このような構造のため、お墓が大きくなりやすいのです。
新人は入口近くで番をする

また、遺体を安置する部屋は「シルヒラシ」といい、お墓の入口を入ってすぐのところに設けられているのが普通です。一説にはお墓に入りたての新人にお墓の番をさせるため、この位置に安置するともいいます。
仮に墓泥棒のような者が入口から入ってきたとたん、棺に入ったご遺体があったら、びっくりして逃げ出すかもしれません。そういうことは想定していないでしょうが、魔除けという考え方はあるかもしれません。
シルヒラシは、遺体が風化していく場所ということもできます。そのために広いスペースが取られます。また、洗骨が済んで骨壺に入れられたお骨は、奥に設けられた棚に安置されます。
この棚は、多い場合は10段以上にもなり、新しいお骨が来ると、古いお骨は奥の方へと上げていきます。そして最終的に三十三回忌を済ませたお骨は、一番奥の広いスペースに合葬されます。
まとめ
このように、沖縄のお墓は門中墓が多くて、入る人が多数に上ること、そして、昔は風葬の習慣があったことなどから、どうしても大きくなりがちだったのです。
県外から来た人にお墓の大きな理由を聞かれたら、このように教えてあげましょう。