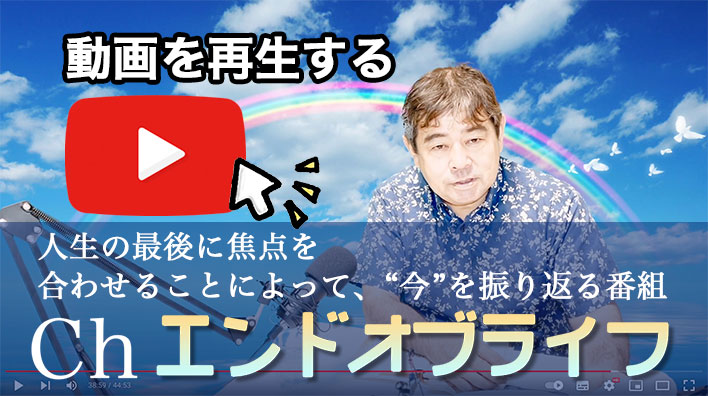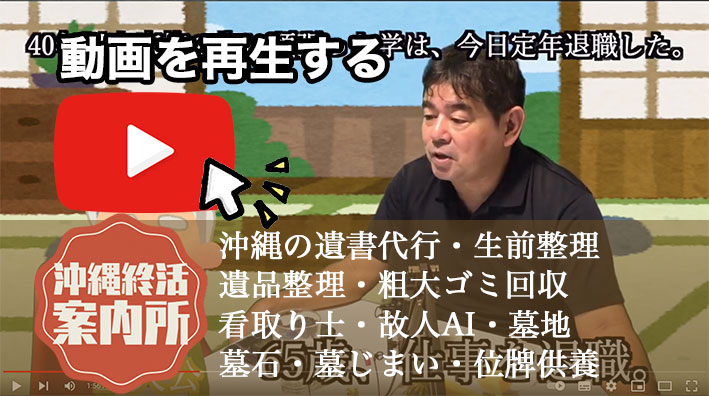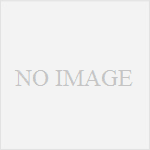1923年(大正12年)の9月1日午前11時58分、関東大震災が発生した。
関東地方をマグニチュード7.9の大地震が襲い、死者・行方不明者10万5000人、家屋全半壊25万戸、焼失家屋21万戸という大災害となった。
この日を忘れることなく災害に備えようと、1960年(昭和35年)に9月1日が「防災の日」として閣議決定された。この日を挟んだ8月30日から9月5日の1週間が「防災週間」となっている。
防災用品点検の日(3月1日・6月1日・9月1日・12月1日 記念日)
防災用品点検の日は、毎年3月1日に設定されており、災害に備えて家庭や職場に備蓄している防災用品の点検を行うことを推奨する記念日です。
この日は、翌日の3月2日が「春の防災の日」であることや、3月に発生した過去の大地震や自然災害を教訓とする意味合いも含まれています。
特に、日本は地震、台風、豪雨などの自然災害が多い国であり、災害時に必要な物資を常に準備しておくことが重要です。
しかし、多くの家庭では、一度防災用品を揃えたまま定期的な確認を行わず、いざという時に使えない状態になっていることが少なくありません。
この記念日を通じて、日常的に防災意識を高め、万が一の災害に備えることの大切さを再認識することが目的とされています。
②点検すべき防災用品とチェックポイント
防災用品点検の日には、以下のような防災グッズの点検を行い、必要に応じて補充や交換をしましょう。
① 食料・飲料水
1人あたり最低3日分(できれば1週間分)の水と食料を確保
賞味期限が切れていないか確認
缶詰、アルファ米、乾パンなどの長期保存食品の補充
ガスコンロやカセットボンベの残量確認
② 衛生用品・医薬品
救急セット(絆創膏、消毒液、常備薬など)の点検
生理用品やおむつ、ウェットティッシュの備蓄
マスクやアルコール消毒液の補充
③ 生活必需品・防災グッズ
懐中電灯やランタンの電池残量確認
携帯充電器(モバイルバッテリー)の充電状況確認
ホイッスルや防災ラジオの動作チェック
耐熱・防寒ブランケットの準備
④ 非常持ち出し袋
家族構成やライフスタイルの変化に合わせて中身を見直し
子どもや高齢者向けの特別な必需品が入っているか確認
貴重品(身分証・保険証のコピー、現金)の整理
このように、防災用品の点検は単なる備蓄確認だけではなく、「いざという時に使える状態にあるか」を確かめることが重要です。
3.家庭や職場での防災意識向上のための取り組み
防災用品点検の日は、個人だけでなく、家庭や職場、地域全体で防災意識を高める機会とすることができます。
① 家族での防災ミーティング
避難経路の確認や、集合場所の再確認
小さな子どもや高齢者がいる場合の対策を話し合う
家の中の安全対策(家具の固定、非常口の確保など)の確認
② 職場や学校での防災訓練
避難経路や非常口の点検、避難訓練の実施
災害発生時の役割分担を決める
AEDや消火器の位置や使い方の再確認
③ SNSやアプリの活用
防災アプリ(Yahoo!防災速報、NHKニュース防災など)をインストール
SNSを活用して家族や職場の安否確認方法を決める
災害時に役立つ情報をシェアする
このように、家庭や職場での話し合いや、地域ぐるみの防災対策を強化することで、災害時の被害を最小限に抑えることができます。
3月1日は、「防災用品点検の日」:まとめ
防災用品点検の日(3月1日)は、非常時に備えて家庭や職場の防災用品を点検し、防災意識を高めるための重要な日です。
由来と意義:日本の災害リスクに備え、定期的な点検を促す日。
点検すべき防災用品:食料・水・衛生用品・防災グッズ・非常持ち出し袋の見直し。
家庭・職場での取り組み:防災ミーティングや避難訓練、SNS活用などで災害対策を強化。
この日をきっかけに、日頃の備えを確認し、大切な家族や地域の安全を守る行動を取りましょう。