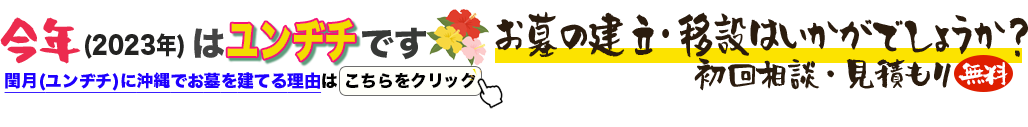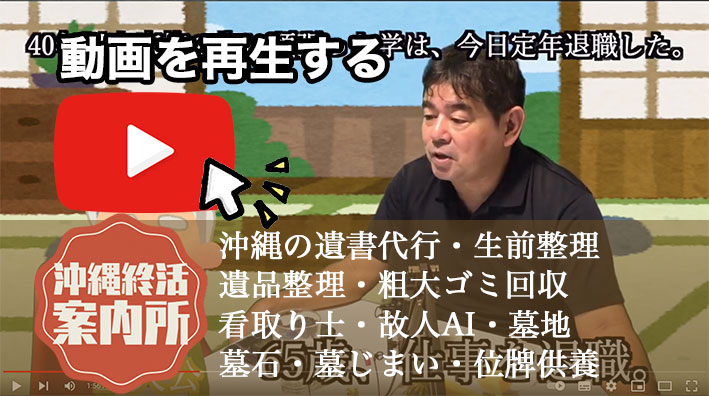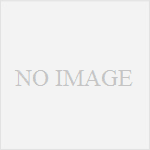終末期にどんな医療やケアを望むのか、患者本人や家族、医師などが事前に話し合う取り組み「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」。いま全国の医療現場などで導入され始めている一方で、課題も見えてきています。どうすれば患者の本心をくみ取れるのか。人生の最後を自分らしく生きるために必要なこととは。さまざまな立場からACPに関わる人たちに伺いました。自分が望む治療やケアを繰り返し話し合う「ACP」話し合ってこそわかる患者の価値観医療者側が気をつけなければならない点も第三者だからこそできる終末期支援話し合いのプロセスから得られる“ACPの種”
自分が望む治療やケアを繰り返し話し合う「ACP」
終末期の医療やケアについて事前に話し合う「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」。英語の「Advance Care Planning」の頭文字をとったもので「事前にケアを計画する」という意味があります。
厚生労働省は2018年、人生の最終段階における医療やケアについてガイドラインを公表。最期まで患者本人の生き方が尊重される医療を実現するため、“人生会議”と愛称をつけACPを推進しています。
背景には、病気やケガなどで命の危機に陥ったとき、およそ7割の人が医療やケアについて自分で決めたり、望みを伝えたりすることが難しくなるという事情があります。
筑波大学附属病院の緩和ケア外来は、ACPを実践している医療現場のひとつです。
この日診察に来たのは、春子さん(仮名・63)。2年前にすい臓がんのステージ4と診断され抗がん剤治療を続けていますが、それが効かなくなればほかに治療法はないと告げられています。
その先、いったいどうすればよいのか不安になり、娘とともに緩和ケア外来を受診しました。
緩和ケア医の木澤義之さんは、厚生労働省のガイドライン作成に携わった、ACPの第一人者です。木澤さんがACPで確認している主な項目は、次のようなものです。
●人工呼吸器や心臓マッサージなどの延命治療を望むかどうか
●最後のときをどこで過ごしたいか
●意識を失ったとき、代わりに誰に意思決定を委ねるか。
以前の話し合いで「延命治療は望まない」と、木澤さんに伝えていた春子さん。この日は、最後のときをどこで過ごしたいか話し合います。
木澤:病気が悪くなったときの対応について、何かお話されたりしましたか?
春子:在宅でできるうちは在宅で。ただ、本当によくよく(悪い状態)になっちゃったら、病院のほうがいいかな。
木澤:その奥底というか、背景にあるものを知っておきたいんですけど。
春子:うちは核家族なので主人と娘ですよね。そのなかで介助、介護させるのは、物理的に難しいかなと感じているのがひとつ。
木澤:やっぱり負担をかけたくない?
春子:そうです。家族には家族の人生、社会との関わり方があるではないですか。そこを縛ってまで、足かせになってまで、面倒を見てもらうのはどうだろうかって。
家族の負担を心配する春子さんに、木澤さんは自宅で過ごす場合にもさまざまなサポートがあることを伝えます。
木澤:必要に応じて、訪問看護もヘルパーさんも行くことができるんです。
春子:何らかの方法があるっていうことですよね。
木澤:実はね、方法はたくさんあるんですよ。上手に、いいところを、折り合いを考えていきたいですね。
「この先どうなるんだろう。薬が効かなくなったときどうなるんだろうとか、そういう話は誰に聞けばいいのかなって思っていたんですね。何よりもゆっくりとお話を聞いていただけると、こんなに気持ちが軽くなるんだなと思いました」(春子さん)
春子さんのACPは、2週間に一度、何度も繰り返し行われます。一度決めたことでも、時がたてば気持ちが変わることがあるためです。
「しっかりご自分で病気のことを聞いて、ご自分で選択していける。患者さんが受けたくない治療を受けないで済むような仕組み、そして望んだ治療を受けられる仕組み。患者さんの意向と一致した治療やケアが提供できることを目指しています」(木澤さん)
筑波大学附属病院 医師 木澤義之さん
話し合ってこそわかる患者の価値観
木澤さんが緩和ケア医として働き始めたのは、1990年代。
当時、医療現場では延命治療を望むかどうかの意思を文書で示す「事前指示書」が導入され始めていました。木澤さんは、心臓マッサージを行うかなどの重要な決断を紙一枚で済ませるあり方に、抵抗を感じたといいます。
「緩和ケア病棟に入院してくる人のほとんどが、希望としては『助かりたいです』と言うんですよ。できれば奇跡が起こって病気が治ればいいのにって。その方に、生命維持治療や心肺蘇生をどうするかという紙を、僕は渡せなかったんです。患者さんの希望を受け止めつつも、病気が治らない可能性があるということを、うまく言語化して、患者さんに伝える技術を僕が持っていなかったんです」(木澤さん)
では、どのように患者の意思を確認すればいいのか。
木澤さんが注目したのが、オーストラリアでの学会で2009年に発表されたACPの研究です。ACPを行うことによって、「終末期医療に満足した」という回答が8割を超えていました。
出典:『The impact of advance care planning on end of life care in elderly patients: randomised controlled trial』(BMJ: 23 March 2010)
その翌年、木澤さんはACPを開発したアメリカの病院へ飛び、臨床現場で学びます。そして帰国後、そこでの経験をもとに日本での実践に乗り出したのです。
「文書には相手がいない。でも、話し合いには相手がいて、深く理解できる。つまり、ストーリー性がそこにはあるし、その奥の価値観を理解することが非常に大きいんです。この人はどんな価値観に基づいて、こういう理由でこう考えるんだ、ということが話し合いによってよくわかります」(木澤さん)
その後、国も、木澤さんが取り組み始めたACPに注目。2018年には、終末期の医療やケアについてのガイドラインで取り上げるなど、全国に広げていこうとしています。
医療者側が気をつけなければならない点も
医療現場で模索が始まっているACP。しかし、その状況に懸念を感じている専門家もいます。鳥取大学医学部准教授で生命倫理や死生学が専門の安藤泰至(やすのり)さんです。
安藤さんは、医師や看護師、重い病を抱える人などと対話を重ね、終末期医療のあり方を考えてきました。
その立場から、医療関係者が主導するACPは、患者の本音を引き出すことが難しいのではないかと指摘します。
「医師・医療者と患者・家族の間は、対等な関係ではなくて、ある種の権力関係がある。患者さんやご家族はすごく不安なわけです。医療者から『決めるのはあなたですよ』と言われても、余計に不安になってくる。医療者自身は自分が誘導しているとか、自分の考えを押し付けているという考えを持っていないかもしれませんが、患者さんたちは(医療者が)引っ張っていってくれたほうが乗りやすいみたいなところがあって、ちょっと危険じゃないかなと思うんですよ」(安藤さん)
鳥取大学医学部准教授 安藤泰至さん
加えて安藤さんが特に懸念しているのは、ACPのなかでの、「延命治療」という言葉の使われ方です。
「本来、医学や医療は人の命を延ばすのが仕事で、字面から言えば、『延命治療』は別に悪い意味ではないわけです。ところが、命は延ばすけれども患者の尊厳を奪うとか、患者が人間らしく生きていくのに役に立たないとか、あるいは過剰な医療であるとか、悪いイメージが言葉の中にくっついて、たとえば『延命治療はどうされますか』と聞かれたときに、それがどういう場面で、どういう治療について聞かれているのか患者はわからないので、『機械につながれて命だけを延ばされるのは嫌です』みたいなかたちで『嫌です』と言ってしまう人が多い。
医師や医療者側は、その答えが自分たちの考えている“よい死のレール”に乗ったものだと捉えて、『ああ、しっかり考えられていますね』と言う。逆に、患者さんたちが『もっと長く生きたい』と執拗に言うと『この人はまだ自分の死が受け入れられていない』とか、『受容が十分ではない』とマイナスな判断をするわけです。
そういう取捨選択みたいなものを医療者側がしてしまうと、患者の本音が受け取られない危険性があることを、医療者側がきちんと知っておく必要があると思います」(安藤さん)
第三者だからこそできる終末期支援
ACPにおいて、患者が本当の気持ちを伝えられるようにするにはどうすればよいのか。医療者とは違う視点を持つのは、ジャーナリストの金子稚子(わかこ)さんです。終活ジャーナリストとして、ACPを行う患者のサポートをしています。
金子さんは11年前、夫・哲雄さんを病気で亡くしました(享年41)。哲雄さんは、流通ジャーナリストとしてメディアでも活躍していました。
肺カルチノイドという病気が進行し、余命わずかと告げられますが、最後まで仕事に全力を注ぐことを望んだといいます。その思いを、医師とも家族とも違う距離感で支えたのが哲雄さんのマネージャーでした。
金子稚子さんと夫・哲雄さん
「私は『ともかく仕事を休んでほしい、療養に専念してほしい』という気持ちでいっぱいでしたが、金子のマネージャーさんが、夫の話をすごく聞いてくださって、最後の最後まで本人の『仕事をしたい』という気持ちを支えてくださっていたと思います」(金子さん)
金子さんは、マネージャーがいてくれたことで夫が最後まで働き続けられるよう治療や暮らしを調整していくことができたといいます。
「やっぱりお医者さんではない人、医療従事者ではない人が近くにいることは非常に重要で、特殊な状況になっている家族と本人の間に風穴を開けてくれる存在なんですよね。」(金子さん)
この経験から金子さんは、ACPには患者や家族、医療者以外に、「第三者」が話し合いに加わるべきだと考えました。いま、みずからその役割を果たそうと、終末期の患者や家族の相談に乗ったり、対話の会を開いたりしています。
「なるべく緊張しない状態で問いかけをしながら、大事にしたいことを言葉にしていくような支援は、第三者じゃないとできないと思っています。質問がないと言葉にできないし、『それってどういうことですか』とか、そういうやりとりで話した自分の言葉で『あっ、そうだったんだ』と気がつく人も多い。そのお手伝いをしています」(金子さん)
話し合いのプロセスから得た“ACPの種”
一方、在宅医療の現場でも、患者の本当の気持ちをくみ取ろうという努力が続けられています。
軽井沢の診療所で、在宅医療に力を入れている紅谷浩之さんです。年間250人ほどの終末期の患者と接し、毎日数多くの患者の家を訪ねています。
その経験から紅谷さんは、患者が最後にどんな医療やケアを望むのかを、必ずしも決める必要はないといいます。
「たとえば、『もし病気が進んだ場合どうしますか』という話をして『じゃあ、そのときは入院します』とはっきり決めていても、いざそのときが来るともう一回迷ったりします。本当は気持ちが変わってきているんだけど、決めてしまったものに引っ張られてしまうこともある。
決めた通りに進んだはずなのに不本意そうなご本人・家族を見ていると、生活のなかで大事にしたいものとかを話していた方のほうが、いざ変化したり迷ったりしたときも、みんなの納得がある決め方ができるように思うんです」(紅谷さん)
在宅医 紅谷浩之さん
紅谷さんにとってのACPは、いざというときに本当に患者の望む判断ができるよう、ふだんの診療のなかでヒントを集めることだといいます。
日常的に対話を重ねていたことで、患者にとっても家族にとっても、納得のいく最期につながったケースがあります。それは、終末期のがんを患っていた40代の男性患者とのやりとりでした。
「診療を始めて数か月たったときに、楽しみにしていた娘さんのソフトボールの大会があったのですが、それまでは見に行くのを『楽しみ』と言っていたのに、ある日、体調が悪くなっていたのをご自身でも感じられていて『やめておこうかな』っておっしゃった。僕はそれを聞いて『いやいや、だめですよ。行きますよ』って言ったんです」(紅谷さん)
紅谷さんがその言葉に行き着いたのは、 “ACPの種”を集めていたからでした。
「娘さんが小さいときから一緒に練習に付き合ってきて、大会には仕事を休んででも必ず見に行くような患者さんでした。関わっているなかで集めていた『娘さんのソフトボールをどれだけ大事にしているか』と、その日の『やめておこうかな』という言葉が、話し合いのプロセスに合わないんです。なので、僕はプロセスのほうを大事にした。本人は、『ああ、そうですよね。行かなきゃですよね』と言って、我に返ったみたいな感じでした。
実際、大会を見に行って、最後の最後まで応援して、娘さんの大勝を見守って帰って来られたんです。『やめておこう』っておっしゃったときに、僕はハッと『病気に言わされている』と思ったんですよね。本人の判断ではないな、本人らしくなさすぎるなと。
結論というのは意外ともろくて、それよりもプロセスのなかに込められていた“大事にしている思い”のほうが生きてくるなと。振り返ると、それはACPの重要性を感じる出来事でした」(紅谷さん)
終末期に望む医療やケアを事前に話し合うACP。命の終わりが見える前から、私たちにできることはどんなことなのでしょうか。
「僕の経験では、その人らしさや、その人の選択を見つけていくことがACPの種になります。それから考えると、本当に好きなこととかポジティブな話を共有しておくと、終末期の選択をするときに助けになると感じます。『どんなこと好き?』『どんなこと楽しい?』とポジティブな話をする機会をぜひ増やしてもらえるといいですね。家族、友だち、近所の方、飲み仲間とか誰とでもいいので、そういう話をちょっとしておく。それだけでも、ACPにつながるんじゃないかと思います」(紅谷さん)
人生の最後を自分らしく生ききるために、あなたは誰と何を語りたいですか。
“終末期”の生を支える
(1)緩和ケア医・関本雅子さん 息子・剛さんのみとりで気付いたこと
(2)人生の最後を話し合う「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」のいま ←今回の記事
※この記事はハートネットTV 2023年2月13日放送「特集”終末期”の生を支える 第2回 人生の最後をどう話し合うか」を基に作成しました。情報は放送時点でのものです。
https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/789/
記事より転用しました。